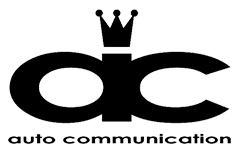発明の日~自動車の歴史~
今日は、特許庁の前身である専売特許条例が制定された日。
=「発明の日」とされています。
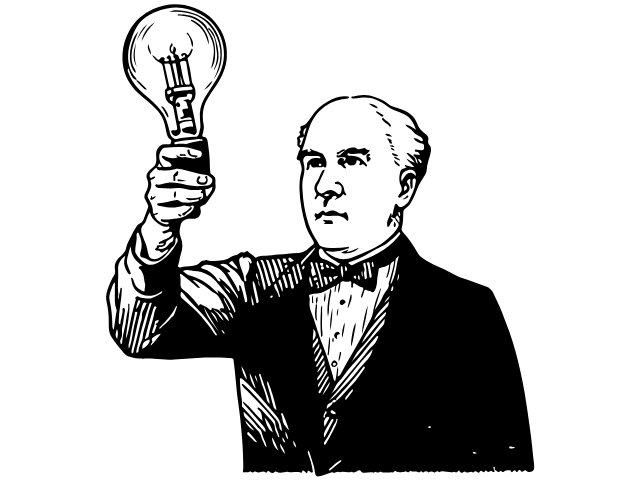
電気の発明と言えばエジソンだけど…
弊社でも愛する車たちをずらりと扱っていますが、自動車の歴史はおよそ150年前までさかのぼります。
今でこそ生活から切り離せない必需品となっている自動車、
だけど実は深く知らない自動車、
仮にも自動車を扱う会社として、それらは知っておかねば!
という訳で今回はこの「自動車の歴史」について少し掘り下げていきたいと思います。
始まりは蒸気からだった
1769年、日本は江戸。馬車や手押し車が主流の時代。
このころのフランスでは、ニコラ・ジョセフ・キュニョーによってはじめて蒸気で走る三輪自動車が作られました。
当時の目的は軍隊で大砲の運搬の為に作られたのが始まりでしたが、重くて遅い、扱いも難しく一般には普及しませんでした。
ガソリン自動車の登場には二人の発明家がいた
時は進み1885年、日本は明治。
ドイツ人発明家のゴットリープ・ダイムラーによりガソリンエンジンを開発。
同時期にカール・ベンツもガソリンエンジンの三輪自動車を発明。
(のちにダイムラーが作った「ダイムラー社」とベンツが作った「ベンツ社」は1926年に合併し「メルセデス・ベンツ」が誕生した)
世界初の実用的なガソリン自動車として知られるのが「ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン」で、最高時速は約16km/h。
三輪構造の後輪駆動でハンドルは今のような丸型ではなく、「舵取り棒」のような形でした。

イメージ写真は丸ハンドル
クラシックカーってカッコイイですよね
当時、カール・ベンツの妻が息子らと100km以上離れた実家まで旅をしたというから驚き。
これが世界初の長距離ドライブとも言われ、道中の燃料補給や修理までこなしたというエピソードも。
この話しから一気に「自動車って使えるんだ!」と認識されたそうです。
大量生産の時代~「革命児T型フォード」
更に時は進み1900年初頭、アメリカのヘンリー・フォード社が量産体制を確立。
車の機能も大きく向上した「T型フォード」を初年度に1万台製造、
それまでは職人の手により1台ずつ手作りするスタイルが主流でしたが、ベルトコンベア式の生産ラインを導入し、作業を効率化。
この大量生産方式が他のメーカーにも広がり、富裕層のみが所有するものから庶民でも手が届く生活の必需品へと変化していきました。

T型フォードモデル
フォードさん、ありがとう…!
技術革新と競争の時代
大衆化が進むに連れ、メーカーはこぞって高機能、ハイスピードな高級車を製造。(ベントレーやアルファ・ロメオなども有名に)
自動車レースも盛んになり、安全性やスピードが飛躍的に高まっていくこととなります。
有名な24時間自動車レース「ル・マン」の初開催は1923年、「モナコ・グランプリ」は1929年に開催されました。
現存国産メーカーで一番古い歴史は…
国内老舗メーカーは1916年創業の、あの耳に残るCMフレーズでおなじみ、トラックで有名ないすゞ自動車です。
世界的企業のトヨタはいすゞの次の1937年創業だそうで、実はいすゞ先輩なんですよね。
当時は乗用車を主力としていた訳ではなかったそうですが、その歴史は100年以上にも渡り、今も日本の自動車産業を支えてくれている会社です。
トヨタのエピソードはご存じの方も多いかもしれませんが、もともとは「豊田自動織機製作所」から自動車部門が分離。
「トヨダ」ではなく「トヨタ」にしたのも、音にした時にスッキリしていて画数が縁起がいいとされたからだそうです。
過去から未来に繋がる系譜
実は日本でも蒸気自動車は古く、フランスから持ち込まれたガソリン車をきっかけに1904年に発明、日本初のガソリン車は白楊社が1907年に完成していました。
当たり前の様に便利さを享受している今日、
これらの時代を経て今があり、更にその先の未来へと続く自動車が進化を遂げています。
新しい革新的な発明により、次世代の技術が日常に浸透していく日はそう遠くない未来かもしれませんね。
そういえば、 大阪・関西万博では空飛ぶクルマのお披露目もありましたね!
未来の乗り物といえば川崎重工の「コルレオ」も展示されているそうで、夢が広がりますね!未視聴の方はぜひYouTubeをご覧ください!テンション上がります!
コルレオに乗るまで死ねない!
↓その他のコラムはコチラから↓